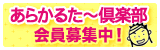|
|
1.はじめに
2.チャンスがあると思うだけでワクワクする 3.有名企業に入れなかったから好きな道に進めた 4.転職の善し悪し 5.悪いひらめきから疑問が生まれる 6.あこがれがあるからパワーがでる 7.ノーと言われて引き下がるなら、本ものじゃない 8.あこがれの人にかたっぱしから会う作戦 9.マイナスからのスタート、ゼロになっただけでもエライ! 10.オンナの自由は30歳から 11.目指すは老人ホームのアイドル 12.もらい上手のコツ 1.はじめに
私の肩書きは“アラカルター”だ。 これを聞いて「?」と思う人も多いと思う。それもそのはず、これは私がつけた肩書きだから。世界広しといえども“アラカルター”を肩書きにしている人は、私しかいない。 この肩書きを使うようになったのは29歳とき。 そのころすでに物を書いてはいたが、簡単な写真を撮ったり、現像したり、素人モデルのコーディネーションをしたり、事務のバイトをしたり…と、まあ今でいうとフリーターに近い生き方をしていた。 「自分に合う仕事は何だろう」 と探してはいたが、ピンと来るものがない。 そんな中で20代半ばごろ、単純にもこんな考えがひらめいた。 「そうだ! なにも今ある仕事にこだわることはない。世の中の需要に合うことに自分の能力を使えばお金になる。それが仕事になるはず。肩書きも自分でつくろう」 こう思いついたら、目の前が明るくなった。 そんなある日、某スポーツ紙でルポを書くことになり、肩書きはどうするかが話題になった。火事場のバカ力じやないが、いざとなると浮かぶもの。 それが“アラカルター”だった。さっそくスピード印刷で名刺を作って、編集長に渡したら、「注釈つけなければわからないようなものはダメだよ。それにフランス語のア・ラ・カルトに英語流にerをつけてもね」とあっけなく却下された。 でも自分を言い表すにはこれしかないと、それからは肩書きを“アラカルター”で通し、最近はペンネームとしても使うようになった。 役所のバイトにはじまり、広告代理店の営業、雑誌やミニコミ誌の編集・記者、選挙事務所のバイト、鉄骨関係の団体組織の事務、怪獣ショーの司会、クラブのクローク、本のセールス、カメラマンのアシスタント…。硬軟、超ヒマな仕事から超忙しい仕事まで、好奇心のおもむくままやってきた。 まさにこれこそ、アラカルターらしい生き方だと思っている。おかげで人間観察もバッチリさせてもらい、おもしろおかしく生きるコツも身につけた。 ア・ラ・カルトとは、フランス料理の1品料理のメニューのこと。ひとりの人間の中にはいろいろな要素(キャラクター)が含まれて、“私”という存在をつくっている。 まさにア・ラ・カルト料理そのもの。 あるときは肉料理のキライな人に、肉いっぱいの料理(自分)をだして嫌がられたり、きれいにデコレーションして、周りをアッといわせたり、でも味が悪くてヒンシュク買ったり――。 おいしい料理に仕上がったなと思っても、いつもいつも気にいられるわけじゃない。ときには思いっきりアク出しをしたり、材料や味付けを変える必要がでてくるかもしれない。 まずいフランス料理にしかなれなかった自分が、試行錯誤を繰り返しおいしいフランス料理に生まれ変わることだってあるのだ。 人生の献立表(メニュー)を考えるのは私。 つくるのも私。 だれもが真似のできない自分だけのオリジナル料理に仕上げるのも私。 アラカルターとは、自分の人生を自分で料理する人のこと。つまり自分らしい生き方を創りだしていく人だ。 「あなたの仕事はなんですか?」と聞かれたら私はこう答えたい。 「私の仕事は生きること、作品は私です」 と。地位も名誉も、お金も、美貌もコネもなし。あるのは人生をガハハと笑って生きるパワーだけ。そんな私の、ときには甘〜く、ときにはしょっぱく、ときには辛いオリジナル料理をちょっとつまみ食いしてください。 2.チャンスがあると思うだけでワクワクする
短大を卒業して、役所でバイトをしていた。 今となっては記憶は定かじゃないが、給料がたしか5万円ぐらいだったと思う。 少ないお金でも、自分の稼いだお金で生活する喜びを感じたのもこのころだった。 仕事はお茶くみとコピー取りがメインのお気軽なものばかり。たまに郵便配達のおじさんが来て、「○○課のかわいこちゃん」なんて喜ばせるような言葉もいってくれる。若いオンナのコなら誰にでもいうリップサービスとわかっていても、まんざら悪い気はしないものだ。 たまに上司が食事やお茶をごちそうしてくれたりもする。 責任のない仕事をしている分には、生意気なことさえいわければ、若いオンナとって職場はけっこう居心地がいいのだ。もう毎日が楽しくて。 「こんないい思いをして、お金までもらえるなんて」休みなんていらないと思ったほどだから、ほんと極楽トンボだ。まだ学生気分が抜けきらず、お遊び感覚で仕事に行っていたのだろう。 でもこの気持も長くは続かなかった。 「こんなことをしていちゃいけない。早くきちんとした職を探そう」 職業意識に目覚めたからかというと、そうじゃない。同じ職場には私と同年代の女子職員がいた。定期的に会議が行われ、彼女はもちろんそれに参加する。その間、バイトの私は残って雑務をしている。なんだか自分だけが取り残された感じがしてさみしくなった。 「だってしょうがないよ。私はバイトなんだから。くやしかったら試験を受けて、職員になればいいんだから」 こんな風に自分を納得させなければいけないことがいやだった。その思いの裏には、 「私だって負けないぐらいの能力があるんだ」とライバル意識が眠っていたのかもしれない。 人をうらやんでウジウジするのは、すごくエネルギーのムダ使い。これぞケチらねばいけない。 そんな気持が芽生えはじめてからは、新聞の求人欄を見て、積極的に職探しをはじめた。 しかし、自分が何に向いているのかはもちろんのこと、何をしたいかさえも思いつかない。実際世の中にはどんな職業があるのかも検討がつかない。 でも好みというものは潜在意識にインプットされていると見えて、新聞の求人広告を ざっと見渡すと、「あっ、ここに入りたいな」と目に留まるものがあった。 気に入った職場の募集があるということだけで、 「私にはチャンスがあるゾ!」とワクワクしてきた。それを見ただけで自分の可能性がどんどん広がっていくような気がした。 まずはチャンスがある。 それだけでもラッキーなんだ。 あとはそれにチャレンジしていくのみと思った。 3.有名企業に入れなかったから好きな道に進めた
しかし求人募集をしているからといって、誰もがすんなりはそこに入れるわけでもない。 相手が求める人材と自分の資質が一致していないとむずかしいのだ。 短大を出たばかりの私が勤めたいと思うのは、社員数も多い大手企業の一般事務だった。 しかしそういうところは競争率も激しい。しかも女性の場合はコネでもないかぎり、親元から通っていないということだけで、書類選考の段階で落とされてしまう。 しかも中途採用でそんなところに入るのはまずむずかしいのだ。 そのころの私は、そんな職場が自分には不向きということにも気づいていなかった。仕事の職種よりも条件のよさそうなところを狙っていたのだ。 自慢じゃないが、20代のころは失業を何度も経験しているが、その都度、戻った履歴書は軽く10通は超えていた。送っては返される、それの繰り返しだった。なかなか面接にもこぎつけない。 どんな会社なのか見てみたいという好奇心も手伝い、「え〜い、どうせダメなら会社だけでも見にいこう」と履歴書を郵送しないで、わざわざ直接持って行ったこともあった。 その会社が街の中心にあって、きれいなビルに入っているというだけで、「こんなところで働けたらいいな〜」といっとき楽しい夢を見てしまう。 まるで買える当てのない新築マンションのモデルルームを見学にいくような気分だった。 今考えると大手企業に入れなくてよかったと思っている。 私が勤めたところは、給料は安くて労働条件もよくないところばかり。だから、そこでの仕事がやりがいのあるものかどうかだけ考えればよかった。 だから転職もしやすかった。 もし、私がだれもがうらやましがるような大手企業に、難しい試験を突破して入ったとしよう。 「○○会社に勤めているんです」 というだけで、いいお見合いの話がくるかもしれない。そこに勤めているというだけで、周りに、 「うあ〜すごい」 とうらやましがられことで、優越感がもてる。自分がいかにもグレードアップしたような気にもなる。 エリートサラリーマンとの出会いも期待できそうだ。 でも仕事にはやりがいが感じられない。たぶん私は毎日、「つまらないな」と夜は友達と飲み歩き、グチをこぼし、有給を利用して海外旅行に行って憂さ晴らしをしていただろう。 「やりがいのある仕事をしたい」 そう思って、悶々とした日々を過ごしていても、やりたいものがはっきりしていないのに、安定した職場を飛び出すなんて恐ろしくてできない。 「会社を辞めたあとに、果たしてこれ以上のところに就職できるだろうか」 いろいろ考えたら迷いも大きくなる。やっとの思いで手に入れた職場ならなおさらそうだ。 なんといっても出来が悪い自分を少しでも立派に見せる仮面はそう簡単には手放せない。 ところが、私は幸か不幸かだれもがうらやむような会社に入れなかった。自分を高く見せるものが何もない。裸の自分で勝負しなければいけなかった。 おかげで給料や労働条件うんぬんというより、やりがいのある仕事か、その職場でどれだけのものが吸収できるかだけを考えることができた。つまり自分の気持に素直に行動ができたというわけだ。 気の多い私にとって、迷うものが少なかったというだけでもハッピーだったと今になって思う。 4.転職の善し悪し
ひところ、転職を繰り返すようなヤツにろくなものはいない、と思っていた。 ところが社会人になった私は、そのろくでもない種族になってしまった。 きわめて常識的な家庭環境で育った私は、転職をするたびにビクビクした。 「こんなに転職を繰り返して、きっとみんなは私のことを何をやってもダメなヤツだと思うだろう」 そんな否定的な気持で親しくしている人達のことを見ていた。 「よそよそしくなってもいいや。私は自分の本質を見てくれる人と付き合いたいんだから」 と開き直ってみても、ちょっと心配だった。 やはり周りが離れていくのはさみしいものだ。自分自身にも自信がもてなくなってくる。 お金はなくなり、生活の不安もでてくる。さらに、今まで親しくしている人が冷たくなってきたら、もうダメージのダブルパンチだ。 ところがどうだろう。自分の不安をよそに、周りの態度は何も変わらなかった。 気にしているのは自分だけだったのだ。 転職しようがしなかろうが、そんなのはうわべのこと。 自分と周りとの関係がそんなことで簡単に切れないことがわかった。 このことを発見できただけでも、転職は大きな収穫だったといえる。 5.悪いひらめきから疑問が生まれる
高校生のころ、「私は結婚運が悪いかもしれない」という思いが突然、天からのお告げのように私の頭の中をよぎった。 なぜこんなことが浮かんだのか不思議だ。 今じゃ、自立するオンナがカッコいいとされているが、このころはまだ“オンナの幸せは結婚”といわれていた時代だ。 オンナのコたちの最大関心事はどんな人と結婚できるかだった。親のしつけもあると思うが、知らずのうちに“結婚イコール幸せ”という図式が頭にインプットされてしまっていたのだ。 なのにこんな言葉がひらめくなんて終わっている。一瞬、気分がクラ〜くなった。 「結婚運が悪い→いいオトコに巡り合えない→幸せになれない」、と私の思考が急スピードで判断したようだ。 私はまだ10代。平均寿命の4分の1も生きていない。これから先は長いのに、これじゃ私の未来に希望がもてない。お先真っ暗。なんだか不幸の烙印を押されてしまったような気がした。 将来のことなんて誰もがわかるわけじゃないんだから、こんなことを勝手に自分で思い込んで気に病むほうがおかしいのだが、悪いことってなぜかいいことよりも信じやすいものだ。 そのころジュニア恋愛小説をよく読んでいたから、悲劇のヒロインの姿を自分にかぶせていたのかもしれない。 だが、そのときふとこんなことを疑問に思った。 「結婚運が悪いからといわれて落ち込むのは、私がオンナだからだ。もし私がオトコならどうだろう。そんなことより仕事運が悪いといわれる方が落ち込むのではないだろうか」 幸せの尺度は世の価値観に左右されるもの。当時は今とは比べものにならないぐらい、仕事ができるというだけでオトコの価値がぐんと上がったものだ。 仕事は自分の努力で目標に近づくことができる、しかし結婚はどうなんだろう。相手があって成立するものじゃないか。自分ひとりでがんばってもどうしようもならないのだ。 ましてオンナは惚れるより、惚れられるほうが幸せといわれ、プロポーズをする優先権はオトコが握っている。結婚ということに関してはどうしても受け身にならざるを得ない。 オトコに好かれるためのルックス、性格……。 なぜオンナだけが自分の幸せを他人に委ねなければいけないの。自分の力で幸せを獲得できないものだろうか。 人との出会いには運が介在する。いくらこんな人と出会いたいと思っても、すぐ現れるものじゃない。 たとえ現れたとしても、その人と結婚できるかどうかわからない。結婚したからといって幸せが保証されるわけでもない。 いったい、「縁とは何? 」 「幸せって何?」 先のことなんてだれもわからない。自分の力でいい運を呼び込むことはできないのだろうか。 これが運というものに関心を持ち始めたキッカケだった。 6.あこがれがあるからパワーがでる
私がいるマスコミ業界は一見、自由で華やかな世界に見える。若いコがあこがれる職業のひとつだろう。 かなり前に私は『さっぽろいい味101店』という本を出して、地元・札幌の書店でベストセラーになったことがある。 本に事務所の連絡先が書いてあったので、いくつか手紙が来た。その中には、若いオンナのコから私の事務所で働きたいというようなものもあった。 そのころ私のところでは男子学生をバイトに使っていたので、ほかに人は必要じゃなかったが、とりあえず会って話をした。 私と同じような仕事をしている友人は、よく彼女を訪ねてくる若いコに「あこがれで仕事はできないんだよ」といっていた。 見た目の華やかさとは違い、現実はむしろ地味できびしいもの、中途半端な気持じゃ務まらないんだよといいたいんだろう。 たしかにそうだ。でも私はいわなかった。 何かを始めたいと思う人にそんな言葉をいうのはナンセンス。むしろ、私は思うのだ。 「どうして? あこがれ大いにけっこう」 すべてのスタートはあこがれが原動力になっているはず。それを否定しちゃいけない。そうなのだ。この私がまさにそうだったから。 その仕事に就きたい、そのためにはどうしたらいいのか。どこから手をつけたらいいかもわからない。 そんなときその業界で活躍している人の話を聞きたくなる。 そう思ったら、躊躇することなくぶつかる。強いあこがれがあるからできるのだ。 いくらあこがれを抱いて、そこの会社に入ろうとしても入れないかもしれない。 むしろその方が多いだろう。たとえ運よく入れてもそのあとにはきびしい現実が待っているのだ。 動機はなんだってかまわない。自分がやってみたいと思う気持こそ大事なのだ。 それが強ければ、自然にパワーも出てくるもの。 当たって砕けて、現実のきびしさは、自分で味わってみることにこそ意味があるのだ。 下見の段階でくじける必要はない。 |